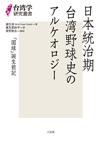|
[目次]
日本語版刊行によせて xvii
序 論 1
1. 研究動機:今日における過去と数字の背後にいる人々―日本統治期台湾野球史のアルケオロジー 2
1.1. 今日における過去―野球史の文脈 2
1.2. 数字の背後にいる人々―行動者は誰か? その動機は? 5
2. 問題意識:体育スポーツの定義と問題としての野球 9
2.1. 体育/スポーツ/体育スポーツの定義 9
2.2. 帝国の体育スポーツとしての野球 14
2.3. コロニアル・モダニティとしての野球―体育スポーツ参加者の観点 20
3. 先行研究 26
3.1. 日治時期台湾野球史の先行研究 26
3.2. 日治時期台湾体育スポーツ史に関する先行研究 34
4. 体育スポーツ史研究の資料、研究方法について 37
4.1. 資料の応用と分析概念 37
4.2. 日治時期野球の文献史料 39
4.3. 野球口述史の発展 42
4.4. 物質文化の手法と図像資料の分析 46
5. 本書の構成 49
第1部 帝国の体育スポーツ―中央と周縁、競争と協力 53
第1章 台湾体育協会と野球行政体制 55
1. 台湾体育協会設立以前の野球組織―「北部野球協会」を例に 56
1.1. 1910年前後の野球の発展 56
1.2. 「北部野球協会」の設立 61
1.3. 「北部野球協会」の主な活動 66
2. 台湾体育協会と野球競技の統合 68
2.1. 体協の設立目的とその人事 68
2.1.1.体協成立の要因 68/2.1.2.体協設立趣旨 69/2.1.3.体協の組織と人事構成 71
2.2. 体協の経費 74
2.2.1.体協会費の徴収と募金 74/2.2.2.当局や財団法人からの補助 76
2.3. 体協野球部の野球事業 79
2.3.1.各種大会の主催 79/2.3.2.大会の権威確立 82
2.4. 体協野球部と野球統制 83
2.4.1.「野球統制令」と台湾野球の発展 83/2.4.2.体協と野球用具管理 86
2.5. 公平性を疑われる仲裁者 87
3. 台湾体育協会支部と地方野球事務の推進 89
3.1. 体協支部の組織と人事 89
3.1.1.体協支部の設立 89/3.1.2.体協支部の人事 92
3.2. 体協支部の経費 94
3.2.1.体協各支部の運営と政府の補助 94/3.2.2.体協会員/会費と台湾人の役割 96
3.3. 体協支部野球部の事業 99
3.3.1.体協支部の人事 99/3.3.2.体協支部野球部と分会の事業 101/3.3.3.体協支部野球部の地方野球スポーツに対する影響―台南、嘉義を例に 104
結び 107
第2章 植民地帝国野球世界の構成 111
1. 「武士道野球」の形成 112
1.1. 武士道野球の基礎:「一高野球」 112
1.1.1.武士道野球の基礎:「一高野球」 112/1.1.2.「野球害毒論」論争と「武士道野球」 114
1.1.2.1.野球害毒論の発生とその内容 114/1.1.2.2.「武士道野球」論の変遷 115
1.2. 「全国中等学校優勝野球大会」と武士道野球の普及 118
1.2.1.「全国中等学校優勝野球大会」の価値と普及 118
1.2.1.1.「全国中等学校優勝野球大会」と大衆娯楽の波 118/1.2.1.2.「全国中等学校優勝野球大会」の趣旨と価値 119/1.2.1.3.「全国中等学校優勝野球大会」の儀式―精神がいかに「可視化」されたか 121
2. 植民地帝国の野球世界と「武士道」野球精神 124
2.1. 植民地帝国スポーツ世界の中心と周縁―明治神宮競技大会を例に124
2.1.1.挙国貢献と明治神宮の建立 124/2.1.2.「中心へと向かう巡礼の旅―明治神宮競技大会 126
2.2. 台湾における「全国中等学校優勝野球大会」 130
2.2.1.「全島中等学校野球大会」と植民地帝国の野球世界 130/2.2.2.「全島中等学校野球大会」の価値と儀式 133
2.2.2.1.「全島中学校野球大会」の価値 133/2.2.2.2.「全島中等学校野球大会」の舞台:儀式と観衆 138
3. 植民地帝国の野球「巡礼」と人材の移動―「六大学」訪台と台湾における「六大学」出身選手を例に 143
3.1. 「六大学」リーグ訪台とその成績 143
3.1.1.「六大学」訪台試合の実施 143/3.1.2.「六大学」訪台の対戦成績146
3.2 台湾における「六大学」出身野球選手の地位 148
3.2.1.指導者的役割 148/3.2.2.台湾人にとっての「六大学」 151
結び 153
第3章 「嘉農」野球と「三民族」の運動競合 157
1. 「三民族」野球チームの構成―内部統合の観点から 158
1.1. チーム結成から甲子園の舞台へ 158
1.1.1.「三民族」の学校 158/1.1.2.嘉農野球部の結成 160/1.1.3.1931年以降の嘉農野球 164/1.1.4.嘉農へのサポート 169
1.2. チームの内部統制―先輩後輩制とスパルタ式練習 170
1.2.1.民族の差異に代わる学校文化―先輩後輩制 170/1.1.2.一視同仁の猛練習 174
1.3. 農業人の野球魂 177
1.3.1.持たざる者の勝利への道 177
2. 同化政策と「三民族」の嘉農野球史 182
2.1. 内台融和の模範―「三民族」と嘉農野球 182
2.1.1.体育スポーツの同化ロジック 182/2.1.2.植民地統治と同化の模範―「三民族渾然融合した異色チーム」 185/2.1.3.霧社事件後の理蕃政策と嘉農野球 188/1.1.4.嘉農へのサポート 169
2.2. 「他者」の身体想像 191
2.2.1.文明化される野蛮な身体―能高団 191/2.2.2.他者の身体想像―俊足、強肩、怪投 193
2.3. 「真の台湾野球チーム」―『台湾新民報』の観点 198
3. 嘉農対嘉中―野球における衝突、和解、共感 203
3.1. 学校対抗の競争文化―嘉農と嘉中 203
3.1.1.後続勢力―嘉中野球部の創部と二度の全島優勝 203/3.1.2.嘉農と嘉中の対抗―嘉義の早慶戦 205/3.1.3.対外試合の対抗文化―学校の名誉を巡る争いとエリート意識 206
3.2. 競争制度下の他者分類と同調集団 211
3.2.1.他者の分類と想像―日本人の嘉中、台湾人の嘉農 211/3.2.2.地方アイデンティティ―嘉農も嘉中も嘉義の代表 213/3.2.3.運動競技の衝突、和解、共感 215
結び 216
第2部 コロニアル・モダニティ 221
第4章 台湾人のスポーツ観 223
1. 排除と包摂、拒否と受容―日治前期(1895-1920)の体育スポーツ 224
1.1. 体育スポーツの民俗活動に対する排除と包摂 224
1.2. 体育スポーツへの対応―排除から受容へ 228
1.2.1.日治初期の体育スポーツ観 228/1.2.2.体育スポーツ観の転換 230
1.3. 体育スポーツ論―身体の健康から国力強化へ 232
1.3.1.健康な身体 232/1.3.2.個人から集団へ 233
2. 1920年代政治社会運動の中の体育スポーツ 236
2.1. 体育スポーツの普及 236
2.2. 身体の健康から「国際舞台で一角を占める」まで 238
2.3. 労働の基礎とレジャーの手段 241
2.4. 資源分配の公平性と運動の合理性に関する批判 242
3. 台湾人の野球認識 245
3.1. 野球反対の理由―健康への影響と運動無用論 245
3.1.1.危険な「柴球」と運動障害 245/3.1.2.運動無用論と「ブルジョア」批判 247
3.2. 児童の野球―「模倣」のモダニティ 250
3.3. 漢詩人コミュニティの野球観 253
3.3.1.漢詩人コミュニティの通俗化、モダニティの実践、転化 253/3.3.2.漢詩に描かれた野球―『台南新報』「文輝閣第二期徴詩 野球」を例に 254
3.4. 野球選手の価値観―心身訓練、チームワーク、社交手段 259
結び 261
第5章 野球選手の身体技能とアイデンティティ 265
1. 公学校野球の発展とその価値 266
1.1. 公学校の体育と競争精神 266
1.1.1.体育における競争精神―公学校規則の体操科「遊戯」を例に 266/1.1.2.学校対抗競技の展開 271
1.1.2.1.公学校運動会の発展 271/1.1.2.2.体育スポーツの競争精神 273
1.2. 日治時期台湾少年野球の発展 276
1.2.1.少年野球の流行 276/1.2.2.少年野球の普及と衰退 277
1.3. 公学校野球コミュニティの形成 282
1.3.1.トレーニング―心身の修練 282/1.3.2.野球の観衆―応援団を例に 286
2. 野球の身体技能とアイデンティティ 291
2.1. 身体技能と植民地の「モダニティ」 291
2.1.1.野球の身体技能 291/2.1.2.競技、スポーツマンシップ、身体技能293
2.2. 公学校野球選手のアイデンティティ 294
2.2.1.公学校野球参加者の社会、経済的背景 294/2.2.2.「徳智体」を兼備した者 295/2.2.3.野球選手のアイデンティティ―自己実現とチームワークの間 296
2.3. アイデンティティ、物質、記憶―優勝旗と記念メダルを例に 299
2.3.1.野球と物質文化 299/2.3.2.優勝旗の物質文化 300/2.3.3.「刻印」される記憶―「第一回全島少年野球大会」優勝メダルを例に 302
3. 勝敗の間―植民地とスポーツ競技 305
3.1. 勝敗の解釈 305
3.1.1.公平と不公平―公平なルールと不公平な審判 305/3.1.2.「勝つより負けるほうがいい」と「得難い勝利」 307
3.2. 勝利の意義―「第一回全島少年野球大会」を例に 309
3.2.1.高雄制覇 309/3.2.2.全島大会で優勝 311/3.2.3.優勝の余波 315/3.2.4.日常生活実践における抵抗と文化統合 318/3.2.5.学校外の日常生活における日台野球関係 321
結び 323
第6章 軟式野球とレジャースポーツ 327
1. 軟式野球の「制度」―技術、試合制度、出場者 328
1.1. 軟式野球と硬式野球の差異 328
1.1.1.軟式野球の技術 328/1.1.2.軟式、硬式の用具の価格差 330/1.1.3.技術面、資本面でハードルが低い軟式野球 331
1.2. 軟式野球の体制、大会制度、出場者規則 332
1.2.1.組織体制化の推進―「軟式野球協会」の誕生 332/1.2.2.軟式野球の大会制度―リーグ制、レベル別対抗戦、シーズン制の誕生 335/1.2.3.出場者規定―年齢制限、身分制限 338
1.3. 軟式野球チームの結成と運営 340
1.3.1.軟式野球チーム結成の背景と流動性 340
1.3.1.1.軟式野球選手の背景 340/1.3.1.2.軟式野球チームの流動性 342
2. 軟式野球の価値と秩序 344
2.1. 余暇の時間と経済的基礎 344
2.1.1.余暇の「出現」 344
2.1.1.1.標準時の概念と休暇制度 344/2.1.1.2.余暇時間の娯楽として 345
2.1.2.レジャーの経済的基礎 347
2.1.2.1.家計調査から見る「娯楽費用」 347/2.1.2.2.軟式野球チームの運営費 348
2.2. 自足の価値とスポーツの階層 351
2.2.1.軟式野球の目的と価値 351/2.2.2.野球の儀式と栄光の象徴―開会式と記念章 353/2.2.3.野球用具とスポーツの階層―ユニフォームとシューズを例に 355
3. 倶楽部、青年団、「高砂野球聯盟」―野球と台湾人の娯楽運動 360
3.1. 倶楽部的性格のスポーツ団体―斗六青葉団と宜蘭白英団 360
3.1.1.斗六青葉団 360
3.1.2.宜蘭白英団 363
3.2. 社会教育という名目と青年の娯楽―青年団の野球 366
3.2.1.青年団の成立と機能 366
3.2.1.1.青年団体の設置と初期の発展 366/3.2.1.2.文教局の設置と官製青年団 368
3.2.2.青年団のスポーツ活動と野球 370
3.2.2.1.青年団のスポーツ活動 370/3.2.2.2.青年団と野球 373
3.2.3.青年アスリートの自己実現と人生への焦慮―九曲堂青年団第二分団陸季盈を例に 374
3.2.3.1.九青団二分団の野球活動 374/3.2.3.2.運動への没頭と自己実現 377/3.2.3.3.逸楽と焦慮の間―体育スポーツの二側面 379
3.3. 「高砂野球聯盟」と娯楽の「もう一つの制度」 381
3.3.1.高砂野球聯盟の成立 381
3.3.2.高雄都市部台湾人給料階級のスポーツと娯楽 386
3.3.3.高砂野球聯盟の学生プレイヤー 388
結び 392
第7章 野球の大衆化―ラジオ、新聞、野球場 397
1. ラジオ事業と野球中継 398
1.1. 日本内地のラジオ事業と野球中継 398
1.1.1.日本のラジオ事業の始まりと全国放送網の形成 398/1.1.2.野球生中継の始まり 399/1.1.3.技術面、資本面でハードルが低い軟式野球 331
1.2. 台湾におけるラジオ事業の発展 400
1.2.1.台湾ラジオ事業の始まり 400/1.2.2.ラジオ聴取者コミュニティの形成 401
1.3. 台湾における野球中継の考察 402
1.3.1.台湾の野球ラジオ中継 402/1.3.2.集中的な野球中継―1932年のケース 403
1.4. 野球中継の聴衆 406
2. 新聞メディアと野球ニュースの読者 410
2.1. 野球記事の内容 410
2.1.1.野球関連ニュース量の趨勢分析―漢珍版『台湾日日新報』検索システムを参考に 410/2.1.2.1920年代初期の野球記事 412/2.1.3.1930年代の野球記事 413
2.1.3.1.野球記事の増加と多様化 413/3.1.3.2.即時的な試合、放送予定記事 416
2.2. 野球記事の読者 417
2.2.1.新聞大衆化の中の台湾人読者 417/2.2.2.読者は誰か―『台湾日日新報』「野球懸賞」の読者分析を例として 419
2.2.2.1.「野球懸賞」の実施 419/2.2.2.2.「野球懸賞」応募読者の分析 421
3. 野球設備と大衆化する野球―野球場の建設、利用を例として 424
3.1. 野球場の変遷と建設 424
3.1.1.1920年代以前の公園付属型球場 424/3.1.2.1930年代の野球場建設計画 425/3.1.3.『台湾新民報』から見た公共資源の分配とその批判430
3.2. 野球場の観客 431
3.2.1.入場券というハードル 431/3.2.2.観客席の階層―チケット購入と未購入、観客席と非観客席 433
結び 439
終 章 443
1. 野球と植民地台湾 444
2. 前記、その後の道―野球は国球 452
解説 菅野敦志 456
参考文献 467
訳者あとがき 488
目次掲載用
日本語版刊行によせて
序 論 1
1. 研究動機:今日における過去と数字の背後にいる人々―日本統治期台湾野球史のアルケオロジー 2
1.1. 今日における過去―野球史の文脈 2
1.2. 数字の背後にいる人々―行動者は誰か? その動機は? 5
2. 問題意識:体育スポーツの定義と問題としての野球 9
2.1. 体育/スポーツ/体育スポーツの定義 9
2.2. 帝国の体育スポーツとしての野球 14
2.3. コロニアル・モダニティとしての野球―体育スポーツ参加者の観点 20
3. 先行研究 26
3.1. 日治時期台湾野球史の先行研究 26
3.2. 日治時期台湾体育スポーツ史に関する先行研究 34
4. 体育スポーツ史研究の資料、研究方法について 37
4.1. 資料の応用と分析概念 37
4.2. 日治時期野球の文献史料 39
4.3. 野球口述史の発展 42
4.4. 物質文化の手法と図像資料の分析 46
5. 本書の構成 49
第1部 帝国の体育スポーツ―中央と周縁、競争と協力 53
第1章 台湾体育協会と野球行政体制 55
1. 台湾体育協会設立以前の野球組織―「北部野球協会」を例に 56
1.1. 1910年前後の野球の発展 56
1.2. 「北部野球協会」の設立 61
1.3. 「北部野球協会」の主な活動 66
2. 台湾体育協会と野球競技の統合 68
2.1. 体協の設立目的とその人事 68
2.2. 体協の経費 74
2.3. 体協野球部の野球事業 79
2.4. 体協野球部と野球統制 83
2.5. 公平性を疑われる仲裁者 87
3. 台湾体育協会支部と地方野球事務の推進 89
3.1. 体協支部の組織と人事 89
3.2. 体協支部の経費 94
3.3. 体協支部野球部の事業 99
結び 107
第2章 植民地帝国野球世界の構成 111
1. 「武士道野球」の形成 112
1.1. 武士道野球の基礎:「一高野球」 112
1.2. 「全国中等学校優勝野球大会」と武士道野球の普及 118
2. 植民地帝国の野球世界と「武士道」野球精神 124
2.1. 植民地帝国スポーツ世界の中心と周縁―明治神宮競技大会を例に124
2.2. 台湾における「全国中等学校優勝野球大会」 130
3. 植民地帝国の野球「巡礼」と人材の移動―「六大学」訪台と台湾における「六大学」出身選手を例に 143
3.1. 「六大学」リーグ訪台とその成績 143
3.2 台湾における「六大学」出身野球選手の地位 148
結び 153
第3章 「嘉農」野球と「三民族」の運動競合 157
1. 「三民族」野球チームの構成―内部統合の観点から 158
1.1. チーム結成から甲子園の舞台へ 158
1.2. チームの内部統制―先輩後輩制とスパルタ式練習 170
1.3. 農業人の野球魂 177
2. 同化政策と「三民族」の嘉農野球史 182
2.1. 内台融和の模範―「三民族」と嘉農野球 182
2.2. 「他者」の身体想像 191
2.3. 「真の台湾野球チーム」―『台湾新民報』の観点 198
3. 嘉農対嘉中―野球における衝突、和解、共感 203
3.1. 学校対抗の競争文化―嘉農と嘉中 203
3.2. 競争制度下の他者分類と同調集団 211
結び 216
第2部 コロニアル・モダニティ 221
第4章 台湾人のスポーツ観 223
1. 排除と包摂、拒否と受容―日治前期(1895-1920)の体育スポーツ 224
1.1. 体育スポーツの民俗活動に対する排除と包摂 224
1.2. 体育スポーツへの対応―排除から受容へ 228
1.3. 体育スポーツ論―身体の健康から国力強化へ 232
2. 1920年代政治社会運動の中の体育スポーツ 236
2.1. 体育スポーツの普及 236
2.2. 身体の健康から「国際舞台で一角を占める」まで 238
2.3. 労働の基礎とレジャーの手段 241
2.4. 資源分配の公平性と運動の合理性に関する批判 242
3. 台湾人の野球認識 245
3.1. 野球反対の理由―健康への影響と運動無用論 245
3.2. 児童の野球―「模倣」のモダニティ 250
3.3. 漢詩人コミュニティの野球観 253
3.4. 野球選手の価値観―心身訓練、チームワーク、社交手段 259
結び 261
第5章 野球選手の身体技能とアイデンティティ 265
1. 公学校野球の発展とその価値 266
1.1. 公学校の体育と競争精神 266
1.2. 日治時期台湾少年野球の発展 276
1.3. 公学校野球コミュニティの形成 282
2. 野球の身体技能とアイデンティティ 291
2.1. 身体技能と植民地の「モダニティ」 291
2.2. 公学校野球選手のアイデンティティ 294
2.3. アイデンティティ、物質、記憶―優勝旗と記念メダルを例に 299
3. 勝敗の間―植民地とスポーツ競技 305
3.1. 勝敗の解釈 305
3.2. 勝利の意義―「第一回全島少年野球大会」を例に 309
結び 323
第6章 軟式野球とレジャースポーツ 327
1. 軟式野球の「制度」―技術、試合制度、出場者 328
1.1. 軟式野球と硬式野球の差異 328
1.2. 軟式野球の体制、大会制度、出場者規則 332
1.3. 軟式野球チームの結成と運営 340
2. 軟式野球の価値と秩序 344
2.1. 余暇の時間と経済的基礎 344
2.2. 自足の価値とスポーツの階層 351
3. 倶楽部、青年団、「高砂野球聯盟」―野球と台湾人の娯楽運動 360
3.1. 倶楽部的性格のスポーツ団体―斗六青葉団と宜蘭白英団 360
3.2. 社会教育という名目と青年の娯楽―青年団の野球 366
3.3. 「高砂野球聯盟」と娯楽の「もう一つの制度」 381
結び 392
第7章 野球の大衆化―ラジオ、新聞、野球場 397
1. ラジオ事業と野球中継 398
1.1. 日本内地のラジオ事業と野球中継 398
1.2. 台湾におけるラジオ事業の発展 400
1.3. 台湾における野球中継の考察 402
1.4. 野球中継の聴衆 406
2. 新聞メディアと野球ニュースの読者 410
2.1. 野球記事の内容 410
2.2. 野球記事の読者 417
3. 野球設備と大衆化する野球―野球場の建設、利用を例として 424
3.1. 野球場の変遷と建設 424
3.2. 野球場の観客 431
結び 439
終 章 443
1. 野球と植民地台湾 444
2. 前記、その後の道―野球は国球 452
解説 菅野敦志 456
参考文献 467
訳者あとがき 488 |