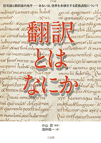|
[目次]
序
第1章 翻訳の記号論序説:社会、文化、そして言語にとって等価性とは何か
導入
第1節 翻訳論と記号論
第1節第1項 翻訳研究における等価性
・等価性の一般理論とカテゴリー
第1節第2項 パース記号論における等価性とヤコブソンの記号間翻訳論
・等価性とカテゴリー化
第1節第3項 聖なる言語:ユダヤ教とアラム語、クルアーンと正則アラビア語
・『バーヒールの書』、『創造の書』、『ゾーハルの書』:カバラー研究と文字、神性、宇宙論
・イスラームと神聖言語:クルアーンと翻訳・解釈・注釈
第1節第4項 神学者シュライアーマハーの解釈学:言語相対主義と文献学
第2節 聖書解釈と近現代アメリカ・プロテスタント主義
第2節第1項 自由主義神学と保守主義神学の分裂と生成
第2節第2項 福音主義からディスペンセーション主義へ
・ディスペンセーション主義:導入
・自由主義神学の分身としてのディスペンセーション主義
第2節第3項 復興主義と啓蒙主義
・福音主義:暫時的総括
第2節第4項 超教派性と福音主義
第3節 ペンテコステ運動、原理主義、テレヴァンジェリズム、民族原理主義
第3節第1項 ペンテコステ運動の勃興
第3節第2項 原理主義と福音主義
第3節第3項 原理主義と社会的福音運動
第3節第4項 テレヴァンジェリストの歴史:新福音主義、ビリー・グラハムとその後の展開
第3節第5項 原理主義の「大転換」とその意義
第3節第6項 現代日本の民族原理主義:オカルト、ハルマゲドン、密教的人類学
第4節 ユージン・ナイダの聖書翻訳論:保守主義神学・現代福音主義と構造言語学との相同的親和性
第4節第1項 SIL (Summer Institute of Linguistics)および WBT (Wycliffe Bible Translators)の宣教と翻訳:
あるいはイーミックの言語学/人類学
・ SIL / WBT における聖書翻訳の近代言語イデオロギー
・ SIL / WBT :福音主義と構造言語学の邂逅
第4節第2項 【聖書 = 母語 = 翻訳】の三幅対
第4節第3項 動態的等価性:目標テクストにおける言及指示内容の「自然さ」
第4節第4項 変形文法『アスペクト』モデルの翻訳論
第4節第5項 ナイダ以後
第5節 修辞学的伝統
第5節第1項 キケロの翻訳論
・地中海世界のリンガ・フランカないし覇権言語の地位をめぐる競合:ギリシア語とラテン語の社会言語学的
分布とその変移の概要
第5節第2項 ヒエロスムスと中世のキリスト教的翻訳論:聖書解釈学、メタ語用、俗語翻訳
第5節第3項 「母語」という思想
第5節第4項 言語の等価性と民族言語文化相対主義
第6節 翻訳研究、言語人類学、コミュニケーション論
第6節第1項 エスノポエティクスの翻訳論
第6節第2項 翻訳研究、システム理論、機能主義的社会学
・システム理論
・スコポス理論
第6節第3項 結語
第2章 翻訳と翻訳研究の構成:記号論的考察
第1節 翻訳研究の「文化論的転回」とは何だったのか:記述学派とその批判について
第1節第1項 テルアビブ学派:翻訳規範論とポリ・システム理論
第1節第2項 記述学派によるロシア形式主義の受容とヘブライ語国家としてのイスラエルの形成
・ポグロム
・ヘブライ語復興運動:言語政策
・ポグロム、移民、同化、民族ナショナリズム:社会政策、社会変容、言語選択
・総括:ロシアとイスラエル、翻訳
・記述学派の系譜、限界、余波
第1節第3項 現代翻訳研究の概観:記号論的総括
第2節 言語復興運動の島々:オセアニア、ピジン/クレオール、エスニック・リバイバル
第2節第1項 土地を翻訳する:メタ語用と翻訳(不)可能性
第2節第2項 ことばの巣とハワイ語復興運動
第2節第3項 マオリ語イマージョン教育とニュージーランド
・総括:ハワイとマオリの民族語復興運動
第2節第4項 ハワイ・クレオール英語
・社会言語学的な等価性の綻び
第2節第5項 ハワイ・クレオール英語の歴史的コンテクスト:メタ語用の審級
第3節 アメリカ合衆国における先住民社会と白人社会との間の法や統治をめぐる対立
第3節第1項 チェロキー・インディアンとジョンソン対マッキントッシュ判決
第3節第2項 インディアンの土地
・土地割当時代
・インディアン再編成法( IRA )とその時代
・アリゾナ州ホピ族と部族評議会
・パパゴ族と部族評議会
・ IRA 以後:揺り戻しと、それへの抵抗としての先住民運動/エスニック・リバイバル
・部族法廷:抵抗と包摂
第3節第3項 総括:翻訳、コンテクスト、メタ語用的フレーム
第4節 翻訳の困難とメタ語用的フレーム:文字、識字、文書、儀礼
第4節第1項 マレーシアの言語政策:マレー語と英語
第4節第2項 南米クンバル社会、北米トロワ社会などにおける文書、儀礼、翻訳
第4節第3項 ズールーの儀礼パフォーマンスと文字の体制
第4節第4項 スラヴ語圏における聖なる(書物の)文字としてのキリル文字とその地政史
・総括:文字、イデオロギー、神聖性
第4節第5項 結語
第3章 近代翻訳論の言語イデオロギー:言語構造、言及指示的テクスト、標準語
第1節「(起点/目標)テクスト」とは何か
第1節第1項 読書という行為とメタ語用的フレーム
第1節第2項 ドイツ・ローマン派と近現代:ゲーテの翻訳論からベンヤミンの純粋言語へ
・近代的翻訳イデオロギー
第2節 文献学的近代、単一言語ナショナリズム:対照ペアと分裂生成 ―― 言語の創出
第2節第1項 ナショナルな諸言語(標準語、国語)の秩序と翻訳
第2節第2項 カロリング朝の言語改革とその余波:島嶼部/大陸、宣教、言語の分裂と定立
・イングランド、アルフレッド大王と俗語の体制
・総括:近代以前における翻訳をとおしたネーションとその言語の形成
第2節第3項 翻訳と二重体/ダブレットの生起
第3節 翻訳における「ポスト・モダン」の一様態:シニカル理性批判
・ピムに見られる現代翻訳研究のイデオロギー
第4節 ポスト・コロニアル翻訳論と、言語の全体
・翻訳の、記号論的 = ヤコブソン的な定義についての注釈
第5節 移民、接触、混淆:翻訳研究と、接触の社会言語学
第5節第1項 ココリーチェと南アメリカのイタリア移民
・ココリーチェとその社会史的コンテクスト
・総括
第5節第2項 スペイン語諸変種の社会言語学的特徴
第5節第3項 総括:ジャンル、メタ語用、イデオロギーと翻訳
第4章 社会文化的な出来事としての翻訳:多様性、多言語性、翻訳不可能性
第1節 導入
・ポスト・コロニアル翻訳理論と記号論
第2節 ディスコース過程、テクスト化/コンテクスト化の社会記号論:擬似翻訳、擬似原典などに見られるメタ語
用、ジャンル、間テクスト性
第2節第1項 メタ語用的テクスト化の連鎖
・間テクスト性と現代翻訳研究
第2節第2項 擬似翻訳( pseudo-translation )
第2節第3項 偽経、そして中国におけるテクストなき/原典なき翻訳(textless translation)
・総括:ナショナリズムとテクストなき/原典なき翻訳
第2節第4項 オシアン詩歌集
第2節第5項 テクストなき/原典なき翻訳:パパゴ・ネーションと英語、大英帝国とペルシア語など
第2節第6項 結語:ディスコース過程と翻訳
第3節 メタ語用的記号過程としての翻訳:翻訳の困難、社会指標性、多言語性の基点としての出来事 ―― 漢文
訓読、ケベック・フランス語、スコッツ語などを事例として
第3節第1項 ヤコブソンの「一般化された翻訳」
・総括:翻訳の記号論、儀礼、社会指標性
第3節第2項 ジュアル(ケベック・フランス語俗語混淆変種)
第3節第3項 クワインの「翻訳不可能性」と社会指標性
・翻訳不可能性、社会言語学的多様性、偶発性/固有性
結 ――多様性の翻訳/翻訳論に向けて――
参考文献
索引
あとがき |